|
T3
Japan
Representative |
一松 信 (京都大学名誉教授) |
|
Conference
Leader |
池田文男
(東京理科大学) |
|
Program Organizer |
半田 真 (東京女学館中学・高等学校) |
|
Program
Organizer |
勢子公男 (東京都江東区深川第四中学校) |
|
Program
Organizer |
光永文彦
(実践女子学園
社会情報教育イノベーション研究所) |
| WorldwideT3
Coordinator |
渡辺 信 (生涯学習数学研究所) |
|
T3
Japan
Administrator |
中澤房紀 (Naoco
Inc./東日本国際大学) |
平成25年度は高等学校を含めて新学習指導要領の完全実施が行われました.この学習指導要領では学習時間が増加され,特に理数教育の充実が求められています.この増加された時間で,旧来の授業を復活するだけでは現在求められている数学教育の目標を達成することはできないでしょう.
もともと,数学は現実の問題を解くことから出発(古代エジプトの測量術)し,それより得られた数学の概念を考察すること(古代ギリシャのユークリッド幾何学)で発展してきました.歴史的にこの関係を繰り返しながら現在を迎えていると考えられます.
この状況を踏まえると,数学教育は
① 数学概念や数学手法を理解する能力
② それを様々な分野に利用し問題解決を図る能力
の2つ育成することにあるといえます.
明治以来の数学を歴史的に考察すると,根底には両方の能力を育成しようとのすることが伺えますが,時代時代によりどちらかの能力の育成が特に強調されて実施されてきたように思われます.昭和40年代の数学教育現代化の時代では①の能力が強調され,その後は,②の能力が徐々に重要視されるように改訂され現在の学習指導要領に継続されています.
明治時代の形式陶冶論に基づくと①の能力を育成すると②の能力は自然に得られると考えられましたが,現在はこの考え方は否定されています.したがって,②の能力を育成するためには,適切な時期に適切な教材が必要になるといえます.
今,様々な問題解決にテクノロジーを使用することは一般的であるといえます.数学教育でも②の能力を育成する教材はテクノロジーを利用することを前提として作成すべきであるといえます.
また,①の能力の育成のためには,数学を頭だけで理解するのではなく,心身すべてで理解することが必要であると考えています.そのためには,テクノロジーが有効であると考えています.
今年度のT^3Japanは,昨年に続き東京理科大学数学教育研究会共催で8月24日(土),25日(日)の2日間東京理科大学で実施することとなりました.夏の暑い日を熱い情熱で ,テクノロジーを用いて数学力および数学応用力の育成を研究したいと考えています.この大会が日本人の数学応用力を育成し,子供たちに適切の数学を使用できるための数学教育に役立つものと信じています。皆様のご参加をお待ちしています.
東京理科大学理学部数学科嘱託教授
東京理科大学数学教育研究会会長
池 田 文 男
|
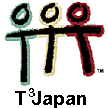
![]()
![]() .
.